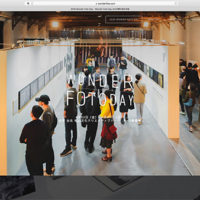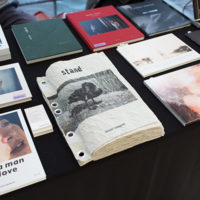【制作ノート – 2020年5月】
コロナ禍の憂鬱と開き直り
2020年1月末、4月に出展予定だった台湾のWonder Foto Day事務局からコロナの影響を受けて会期を延期するとの連絡が届く。まさかと驚く。
2月、横浜御苗場がコロナの影響を受けて延期になり、EMON AWARD展は公開審査が無観客オンライン公開になる。残念だけど、状況を考えたら正しい判断。
3月上旬、一つの可能性として日本にも悲惨な未来——コロナによる医療崩壊や世界大恐慌ほどの経済的な大ダメージがやって来るかもしれないという情報を知って愕然とする。
直感的にもそれが来てしまうように思えて暗い気持ちになる。
その後、時が経つにつれて不安がどんどん現実のものとなり、すっかり気が滅入ってしまう。
どこかで分岐したパラレルワールドに迷い込んでしまったようだ。
4月上旬、仕事が減り家での時間が増えたにもかかわらず、先への不安から制作に身が入らない。
自分にとって果たして一番大切なものはなんなのだろうかと考え続ける。
4月下旬、健康のためマスクをして近所を散歩しながらチェキで気のむくままに撮影する。純粋な撮る喜び。
少しずつ何かを作りたい気持ちが戻ってくる。
5月中旬、世の中が徐々にコロナ共存時代に向けて新しい生活様式を模索する中で、どうせこれからほとんどどの仕事も危機に直面するのだから、だったらやっぱり自分が一番やりたい作家活動を黙々と続けようと開き直る。
神戸の作家さんに連絡したら、こんな中でも順調に作家活動が進んでいることを知る。僕も頑張らないと。
新たな時代の御苗場が始まった。完全オンラインによる展示。先駆者として頑張って!
「stand」の伏流と新たな出発
EMON AWARD展の後、自分の未熟さを痛感する。
現状の「stand」には良いものがあるかもしれないけれど、ほとんどの写真がものになっていない。
根底にあるものを見直して、もう一度地道に撮影からやり直す必要がある。
現状の手製本についてはもったいないけれど、製作を中止し、残りのエディションは世に出さないことを決める。自分が納得できなくなってしまったものを売ることはできない。
standの根底にあるもの。伏流。そして自分が作家として生涯求めるものは果たして何だろうか。
狂おしいほどの生命力そして歓喜、爆発する多様性。
自分の中に眠っている、そんな力を目覚めさせたい。
それは先祖と繋がること。宇宙と繋がること。
飯沢耕太郎氏の「キーワードで読む現代日本写真」をパラパラ見ていて、「物狂い」という言葉にピンとくる。
アニミズム、シャーマニズム、人類学、民俗学、魑魅魍魎、異界、見えない何かが写り込む、在るということの確かな手応え、偶然を偶然でとらえて必然化すること。
物狂いの系譜に連なる作家(本書で挙げられているのは、シャーマニズムの頁に岡本太郎、須田一政、内藤正敏、荒木経惟、津田直、志賀理江子、佐伯慎亮、アニミズムの頁に土門拳、野島康三、安井仲治、小石清、大辻清司、川田喜久治、今道子、うつゆみこ)の作品をじっくり吸い尽くしたい。
コロナ共存時代にどのような撮影ができるだろうか。
遠くに行くことができない日々ではあるが、逆に近くにあるものの深くに行けるチャンスかもしれない。
近所を散歩していても、まだまだ今の自分に見えていないもの、見ようとしていないものがこの町にもたくさんあるのではと思うようになった。
大学時代学んだフィールドワークを思い出して、土地を読み解きながら、その過程で自分の深いものを暴いていくアプローチは一つ有効かもしれない。
自分は大地の一部であり、大地は自分の一部なのだから。
僕なりの道を切り開こう。
村上春樹氏が村上ラジオで、何か大きなことが起こったときにそれを直接的に書くほかに、転換して物語として書くのが作家だというようなことを言っていた。
この時代の空気を吸っていたら、否が応でもコロナ禍の影響が作品に現われる。
どの作家の創作にも、自然と時代の空気はこびりつく。力む必要はない。